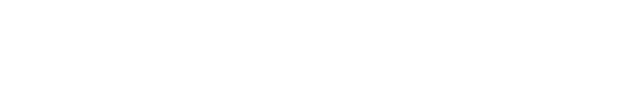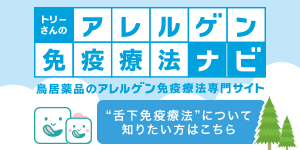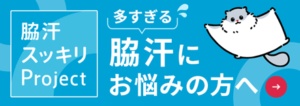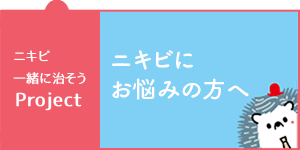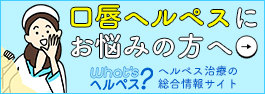顔にイボができたら?原因や放置のリスク、治療法を徹底解説

顔は人の視線が集中しやすいため、小さなイボでも気になってしまうものです。
顔にできるイボにはいくつかの種類があり、それぞれ原因や対処法が異なります。自己判断で放置したり、ケアしたりすることにはリスクがあるため、皮膚科の受診をおすすめします。
そのためには、受診タイミングが分かるよう、顔にできるイボについて詳しく知っておくと役立つでしょう。
この記事では、顔にできるイボの代表的な種類や見分け方、放置によるリスク、そして現在行われている主な治療法などについて説明します。
顔にできるイボの種類

顔に現れるイボには、ウイルス感染によるものと、加齢や体質が関係するものがあります。それぞれの特徴や原因を理解して、適切な対処に役立てましょう。
ここでは、代表的な顔のイボの種類とその特徴などについて詳しく解説します。
よくある顔のイボの種類
顔にできるイボには、ウイルス性と非ウイルス性のものがあり、それぞれに特徴があります。
ウイルス性のイボには以下のようなものがあります。
- 尋常性疣贅
- 青年性扁平疣贅
- 伝染性軟属腫(水イボ) など
このようなイボは、肌の小さな傷からウイルスが侵入して発症することが多いです。
一方、非ウイルス性のイボには以下があります。
- 脂漏性角化症
- 軟性線維腫
- 老人性血管腫 など
このようなイボは加齢や紫外線、摩擦などが原因で発生し、特に中高年に多く見られる種類です。
イボは見た目や触感、発生部位などに違いがあり、自己判断で区別するのは難しいため、気付いたら皮膚科の受診をおすすめします。
ウイルス性と非ウイルス性の違いとは?
イボにはウイルス感染によるものと、非感染性のものに分かれます。
ウイルス性のイボはヒトパピローマウイルス(HPV)や伝染性軟属腫ウイルス(みずいぼウイルス)などの感染が原因で、他人に感染する可能性があります。
一方、非ウイルス性のイボは、加齢や紫外線、摩擦などが原因で発生し、感染性はありません。
しかし、どちらのタイプのイボも見た目や触感だけでは判断が難しいため、皮膚科での診察を受けるようにしてください。
悪性腫瘍との鑑別が必要なケースも
顔にできるイボの中には、見た目が似ているために良性と誤認されやすい悪性腫瘍も存在します。
例えば、基底細胞癌や有棘細胞癌などは、初期にはイボやシミと区別がつきにくいことが少なくありません。
このような悪性腫瘍は、早期発見・早期治療が重要であり、放置すると進行してしまう可能性が高いです。
見た目では判断が難しい
顔にできるイボは、種類や原因によって見た目や触感が異なりますが、見た目だけで正確に判断するのは難しいです。
例えば、ウイルス性のイボと脂漏性角化症は色や形が似ている場合があります。
また、前述の通り悪性腫瘍がイボのように見えることもあり、自己判断で放置すると危険です。
特に、以下のような状態には注意しましょう。
- イボが急に大きくなった
- 色や形が変化した
- 出血や潰瘍が見られる
このような場合は放置せず、早めの皮膚科の受診をおすすめします。
当院では、ダーモスコピー検査(医療用拡大鏡検査)を用いて、肉眼では分かりにくい所見を確認しながら、皮膚腫瘍(できもの:ほくろ・イボ・粉瘤など)の診察にあたっています。
顔にできたイボを放置するリスク

顔にできたイボを放置すると、見た目の変化だけでなく、健康面や心理面にもさまざまなリスクが生じる恐れがあります。
顔は紫外線が当たりやすい露出部という部位であるため、基底細胞癌・悪性黒色腫など紫外線暴露が発生の確率を高める皮膚悪性腫瘍(皮膚がん)に注意が必要です。
ここでは、イボを放置することによる具体的な影響について紹介します。
数が増えたり大きくなったりする可能性
イボを放置すると、数が増えたり大きくなったりしてしまい、見た目に影響が出る可能性があります。
特にウイルス性のイボは、自己感染や他人への感染を引き起こすことがあり、放置することで症状が悪化する恐れも否定できません。
また、イボが大きくなると、治療に時間がかかる場合があります。
小さいうちに皮膚科を受診して、適切な治療を受けましょう。
肌トラブルや見た目の印象への影響
顔にできたイボを放置すると、肌トラブルや見た目の印象に悪影響を及ぼす可能性があります。
イボが目立つ部位にできると、他人の視線が気になり、自己評価の低下やストレスの原因になってしまいかねません。
また、前述のようにイボが大きくなったり数が増えたりすると、メイクで隠しにくくなり、毎日の生活で不便な思いをすることも考えられます。
目立つ部分だからこそ、顔のイボが気になる場合は早めに皮膚科の診察を受け、効果的な治療を進めていきましょう。
自己処理による炎症・感染リスク
イボを自己処理することは、炎症や感染のリスクを高める可能性があります。
無理にイボを引っ掻いたり削ったりすると、皮膚に傷ができ、そこから細菌が侵入して二次感染を引き起こす恐れも否定できません。
自己処理による傷やイボの悪化が起これば、治療の難易度が上がり、完治まで時間がかかってしまったり、跡が残ったりすることもあります。
できたイボが気になる場合は、自己判断せずに皮膚科で処置を受けましょう。
顔のイボの治療法は?

顔にできたイボの主な治療法として、液体窒素による凍結療法、高周波メスや電気焼灼による除去、炭酸ガス(CO₂)レーザーによる切除などが挙げられます。
ここでは、それぞれの治療法の特徴や適応について紹介します。
液体窒素による凍結療法
液体窒素による凍結療法とは、-196℃の液体窒素を用いてイボの組織を凍結させ、壊死させる治療法で、保険診療の対象になっています。主にウイルス性のイボに対して行われます。
治療は2~3週間ごとに繰り返し行われ、数回の通院が必要です。
施術中に痛みを感じることがあり、治療後には水疱やかさぶたができることもあるため、痛みに弱い人は先に医師と相談しておくとよいでしょう。
また、色素沈着や傷跡が残る可能性もあるため、気になる人は施術後のケアも必要です。
高周波メスや電気焼灼による除去
高周波メスや電気焼灼による除去は、電気エネルギーを利用してイボの組織を焼灼し、除去する治療法です。保険診療の対象になっています。
局所麻酔を施した上で行われ、施術時間は短く、出血も少ないのが特徴です。
主に顔や首などのデリケートな部位にも適しているため、顔のイボの悩みにも効果が期待できます。
ただし、施術後に赤みやかさぶたが生じることがあり、色素沈着や傷跡が残る可能性もあるため、術後のケアが重要です。
炭酸ガス(CO2)レーザーによる切除
炭酸ガス(CO₂)レーザーによる切除は、レーザーの熱エネルギーを利用してイボの組織を蒸散させ、除去する治療法です。
主に小さなイボや盛り上がったイボに適しており、施術時間が短く、出血が少ないのが特徴です。
また、周囲の正常な組織へのダメージが少なく、術後の傷跡が目立ちにくい傾向にあります。
施術後には一時的な赤みやかさぶたが生じることがありますが、適切なケアを行うことで、回復を早められます。
炭酸ガス(CO₂)レーザーは、見た目を重視する人や、短期間での治療を希望する人に適した方法です。
ただし、審美目的の場合は自由診療のため、費用は全額自己負担になります。
イボの種類・部位・肌質に応じた治療選択が必要
イボの治療法を選択する際には、イボの種類や大きさ、発生している部位、患者さんの肌質などを総合的に考慮する必要があります。
例えば、ウイルス性のイボには液体窒素療法が適しており、加齢によるイボには炭酸ガスレーザーや電気焼灼が効果的です。
また、顔や首などの目立つ部位では、術後の傷跡や色素沈着を抑えられる炭酸ガス(CO₂)レーザーが向いているでしょう。
治療法は医師が提案しますが、患者さんの希望も考慮されるため、顔のイボ治療についての希望があれば、事前のカウンセリングで伝えるようにしましょう。
顔イボで気になる疑問とその回答

顔にできたイボは、見た目の変化だけでなく、健康面や心理面にもさまざまな疑問や不安を引き起こします。
ここでは、顔のイボについてよくある質問とその回答を紹介します。
Q1:治療したら傷跡が目立ちそう
顔にできたイボを治療したあと、傷跡が目立たないかどうかは多くの患者さんが気にする点です。
イボ治療では術後に赤みや色素沈着、傷跡などが生じる場合がありますが、治療法によってはそのリスクを軽減することも可能です。
液体窒素療法では患部がかさぶたになり、取れたあとに色が残る(炎症後色素沈着)ことがありますが、時間とともに薄れることが一般的です。
炭酸ガスレーザーは周囲の正常な皮膚へのダメージを抑えながら除去を行うため、傷跡が目立ちにくい特徴があります。
成増駅前かわい皮膚科でも炭酸ガスレーザーによるイボ治療を行っています。傷跡がご不安な場合には、お気軽にご相談ください。
Q2:治療の費用やリスクが心配
顔にできたイボの治療に関して、費用やリスクが気になってなかなか治療へ踏み出せないという患者さんもいるかもしれません。
しかし、イボ治療は医療保険が適用される治療法もあるため、費用を抑えながら治療を進められます。
保険診療に該当する治療法としては、液体窒素を用いた凍結療法や電気焼灼法などがあります。
ただし、施術後に傷跡が残ることもあるため、見た目の仕上がりも重視する際には注意が必要です。
炭酸ガスレーザーは自由診療となりますが、傷跡を少なくきれいに顔のイボを取りたい方に向いています。
費用やリスクについて詳しくは医師に相談し、自分の希望に合った方法を選びましょう。
Q3:顔イボの予防方法は?
顔イボを予防するには、日常的なスキンケアと生活習慣の見直しがおすすめです。
ウイルス性のイボは皮膚の小さな傷から感染することがあるため、洗顔時やひげ剃りの際は強くこすらないよう注意します。
また、紫外線は肌への刺激となるため、日焼け止めを使ったり、帽子や日傘で物理的に肌を守ったりする工夫が効果的です。
保湿も重要で、肌の乾燥を防ぐことでバリア機能が保たれ、外的刺激から守りやすくなります。
このほか、栄養バランスのとれた食事や十分な睡眠を心がけることで免疫力を維持し、肌の健康を内側からサポートすることも大切です。
Q4:顔イボは市販薬で取れる?
顔イボを自分で治そうとして市販薬を使用する人もいますが、効果や安全面を考えると、皮膚科での治療がおすすめです。
ウイルス性のイボには、ヨクイニンを含む薬が用いられますが、即効性はありません。
また、脂漏性角化症など加齢に伴うイボには効果が期待できず、むしろ肌に負担をかけて悪化させる恐れもあります。
さらに、市販の外用薬で刺激が強いものを使うと、顔の皮膚に炎症が起きたり色素沈着が残るリスクも考えられます。
「見た目が気になる」「なかなか改善しない」と感じた場合には、市販薬に頼るよりも、皮膚科専門医に相談して適切な治療を受けたほうが高い効果が期待できるでしょう。
Q5:悪い病気だったらどうしよう
多くのイボは良性ですが、中には悪性腫瘍と見分けがつきにくいものも存在するのも確かです。
特に、「短期間で急に大きくなる」「形がいびつ」「色が変わった」「出血がある」といった特徴がある場合には注意しましょう。
このような症状がある場合、悪性腫瘍の可能性があるため、自分で判断せず、まずは皮膚科で診察を受けるのが重要です。
日本皮膚科学会または日本専門医機構が認定した皮膚科専門医による視診やダーモスコピー検査(医療用拡大鏡検査)、必要に応じた生検などを通して、イボの性質を正確に判断することが、適切な対処につながります。
気になる症状に気付いたら、早めに皮膚科専門医が在籍する皮膚科を受診してください。
まとめ
顔にできるイボは、加齢、紫外線、ウイルス感染、摩擦など複数の原因によって発生します。
多くは良性ですが、悪性腫瘍と見分けがつきにくいケースもあり、見た目だけで判断して放置せず、皮膚科を受診しましょう。
また、自己処理でイボを取ろうとすると傷跡が残ったり悪化したりする可能性があるため、やはり皮膚科の受診をおすすめします。
治療法には、液体窒素や電気焼灼、高周波メス、スキャナー付き炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)などがあり、保険診療か自由診療か、治療後の傷跡はどうなるのかなど、目的や希望を考えながら医師と相談して決定しましょう。
成増駅前かわい皮膚科では、顔にできたイボをはじめ、幅広いイボの悩みに対応しています。
傷跡の残りにくい炭酸ガスレーザーを使った治療も可能なため、気になる方はぜひご相談ください。
記事制作監修

成増駅前かわい皮膚科
院長 河合 徹