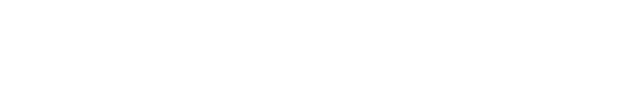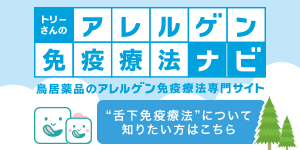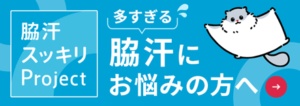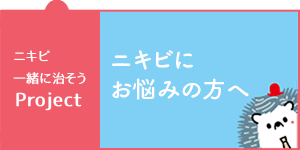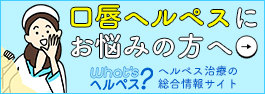ほくろと悪性黒色腫の見分け方は?注目すべき特徴や検査・治療方法などを紹介

ほくろはメラニン色素を作り出すメラノサイトという細胞が変化して塊が形成されたものです。基本的には良性ですが、中には悪性のものもあります。
皮膚がんの発生頻度は、年々増加しているといわれていることをご存じですか?内臓にできる癌とは異なり、皮膚にできるがんは自分で目視できることから、早期発見しやすいとされているため、簡単な見分け方を知っておくことが大切です。
この記事では、悪性黒色腫(メラノーマ)の種類と特徴、ほくろとの見分け方、悪性黒色腫以外の皮膚がんの種類と特徴、皮膚がんの検査方法と治療法を紹介します。
気になるほくろがある方、皮膚がんの特徴を知っておきたい方は、ぜひご覧ください。
悪性黒色腫(メラノーマ)の種類と特徴

『悪性黒色腫(メラノーマ)』とは、皮膚がんの一種でメラニン色素を作り出す役割をになっているメラノサイトががん化したものです。目視や顕微鏡での所見や予後などから主に4つのタイプに分類されます。
ここではまず、悪性黒色腫(メラノーマ)の種類と特徴について解説します。
末端黒子型黒色腫
一般的に、青年から壮年期以降の手のひらや足の裏、爪などに発生することが多いタイプで、特に足の裏にできやすいのが特徴です。機械的な刺激や外傷が原因のひとつだと考えられています。
日本人を含む黄色人種は、他のタイプの悪性黒色腫が発生することが少ないこともあり、この末端黒子型黒色腫が悪性黒色腫全体の4〜5割を占めます。
形がはっきりせず、色が単一ではない褐色もしくは黒褐色のシミができ、数ヶ月から数年かけてシミの中にしこりや潰瘍ができることもあるでしょう。爪の場合は、爪の中に黒褐色の縦線のようなものが通っているように見えることがあります。
悪性黒子型黒色腫
日本人の皮膚がんではもっとも少ないタイプで、高齢者の顔面にできやすいのが特徴です。
色や形が不規則なシミが10〜40年かけてゆっくりと広がるように成長し、その後大きく中央が膨らんでいきます。
長年紫外線を浴び続けることが原因だといわれています。
表在拡大型黒色腫
20歳から高齢者の幅広い年齢で発生し、胴体全体や膝から足首にかけて平たく広がっていくタイプです。
最初は少し隆起したシミのように見えますが、徐々に境界が不明瞭となり、色の濃さもまだらになっていきます。黒色だけでなく赤っぽい色が混ざったり、全体的に赤色になることもあるため注意が必要です。
外へ出かけることが多く、強烈な紫外線を浴びる機会の多い方がなりやすいといわれています。
結節型黒色腫
40〜50代頃に発生することが多く、全身のどこにでも発生する可能性があるタイプです。
短期間で盛り上がるように増殖するのが特徴で、黒色や色がまだらな塊ができますが、初期の段階では色の変化を伴わないこともあります。
他のタイプより悪性度が高く、予後がよくないケースが多いため注意が必要です。
ほくろと悪性黒色腫の見分け方

悪性黒色腫はほくろと似ていることも多く、間違って放置すると病状が進行してしまう可能性があります。
ここでは、ほくろと悪性黒色腫の見分け方を紹介します。
ただし、自己判断で医療機関を受診しないのは危険なことです。気になるほくろがあるときは、早めに医師に相談することをおすすめします。
形状
一般的にほくろは円形や楕円形ですが、悪性黒色腫は非対称でいびつな形をしているケースが多いです。
ほくろと皮膚の境界がギザギザになっていたり、ほくろ周辺の皮膚にまで色がしみ出したりすることがあります。ほくろの中にできものが生じることもあるでしょう。
境界線
悪性黒色腫は周囲の皮膚との境界線が不明瞭であることが多いです。そのため、境界を確認することがほくろと悪性黒色腫を見分けることにつながります。
例えば、墨汁を落としたようにほくろの輪郭がにじんでいる、ぼやけている場合などは悪性黒色腫が疑われます。
色
ほくろの中の色が均一でなく濃淡の差がある場合は、悪性黒色腫の可能性があります。
ひとつのほくろの中に茶色や黒色など異なる色調が混在し、まだらになっている場合は注意が必要です。
また、もともと褐色だったほくろの色が、徐々に濃い黒色へと変化していく場合も、悪性黒色腫が疑われます。
大きさ
ほくろが直径6mm以上の大きさに成長している場合は、悪性黒色腫の可能性があるため注意が必要です。
もともと大きめのほくろの場合はサイズについてそれほど気にする必要はありませんが、2〜3mm程度の大きさだったほくろが、ここ1〜2年で急激に大きくなった場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
成長スピード
悪性黒色腫はほくろと比べて成長スピードが早いのが特徴です。
上述の通り6mmを超えるものは悪性黒色腫の可能性があるとされ、特に急激に大きくなったものには注意が必要です。
また、数が急激に増えた場合も悪性黒色腫の可能性があります。
硬さ
通常、ほくろの硬さは均一ですが、悪性黒色腫の場合は硬さが均一でなかったり、全体的により硬くなっていることがあるため注意が必要です。
爪にも注目する
悪性黒色腫は爪にできることもあるため、皮膚表面にできたほくろだけでなく、爪にも注目しましょう。
爪に悪性黒色腫が生じた場合、爪に黒褐色の線が縦に入り、時間の経過とともに色が濃くなったり幅が広くなったりなどの症状が現れます。
そこから進行すると、爪が割れたり色がしみ出て周辺の皮膚にまで達したりなどの症状が現れることがあります。
悪性黒色腫以外の皮膚がんの種類と特徴

皮膚がんには、悪性黒色腫以外にもいくつかの種類があります。
ここでは、悪性黒色腫以外の代表的な皮膚がんである基底細胞がんと有棘(ゆうきょく)細胞がん、乳房外パジェット病、メルケル細胞がんの特徴を紹介します。
基底細胞がん
基底細胞がんは、日本人に多い皮膚がんの一種で、表皮の最下層にある基底細胞や毛包の細胞ががん化したものです。
見た目はほくろに似ていて、黒色や黒褐色の斑点が集まって盛り上がり、大きくなると中心部分に潰瘍ができることがあります。また、シミのように平面状になっているタイプもあります。
内臓やリンパ節に転移することはほとんどなく、痛みやかゆみを伴うことはありませんが、再発しやすく、放置すると筋肉や骨などの深い組織まで破壊しながら進行してしまう可能性もあるため注意が必要です。
有棘細胞がん
有棘細胞がんは、表皮の有棘層の細胞ががん化したものです。
顔や頭皮などの直射日光を受けやすい部分にできることが多いため、紫外線が原因のひとつだと考えられていますが、やけどの痕や放射線、化学物質、ウイルスなどが原因で発生することもあります。
有棘細胞がんは、皮膚の一部が赤くなり、皮膚表面がカサついて硬くなっていぼのようなしこりができたり、ただれやかいようができたりするのが特徴です。進行すると腫瘍から体液がしみ出て悪臭が発生することがあります。
乳房外パジェット病
乳房外パジェット病は、皮膚のアポクリン腺という汗を作る組織の細胞ががん化したものです。
乳がんの一種に乳房パジェット病という疾患があり、見た目の特徴が似ていることから、乳房外パジェット病という名称になりました。
好発部位は外陰部や肛門周辺、わきの下、へそ周辺などです。ただれやかゆみなどの症状を伴うこともあり、進行すると他の内臓やリンパ節に転移することがあるため注意が必要です。
メルケル細胞がん
メルケル細胞がんは、表皮にあり特定のホルモンを作り出す役割を担っているメルケル細胞ががん化したもので、リンパ節に転移するケースが多いのも特徴です。
肌色または青みがかった赤色で、ツヤのある硬いしこりができ、急速に成長していきますが、痛みを伴うことはほとんどありません。
診断時の平均年齢が75歳であることからもわかる通り、長年紫外線を浴び続けることがメルケル細胞がんのリスクを高めるとされています。ただし、若年者でも免疫機能が低下していると発生することがあります。
皮膚がんの検査方法

悪性黒色腫を含む皮膚がんは、他の内臓やリンパ節などに転移する可能性もあるため、早期に発見して適切な治療を受けることが大切です。
経験豊富な皮膚科専門医であれば、視診のみで診断できることもありますが、判断の難しいものについてはダーモスコピーや皮膚生検、画像診断などの検査を行います。
ここでは、医療機関で行う皮膚がんの検査方法について詳しく紹介します。
ダーモスコピー
ダーモスコピーとは、ライトがついた拡大鏡のような道具です。反射ありと反射なしを切り替えることで、皮膚の表面から真皮の浅層までを詳しく観察するために使います。検査に伴う痛みはありません。
さまざまな皮膚疾患の診断に用いられますが、特に悪性黒色腫や基底細胞がんなどのほくろやシミに似た皮膚がんの診断に有効です。
ただし、すべてのケースで正確に診断できるわけではないため、診断を確定するために皮膚生検を併用することもあります。
皮膚生検
皮膚生検とは、腫瘍の一部もしくはすべてを切り取って病理検査(顕微鏡検査)を行うことです。
切り取った腫瘍から薄い組織切片を作成し、そこにさまざまな薬品で染色して顕微鏡で観察し、組織の構造や腫瘍細胞の特徴から診断を行います。
悪性黒色腫の診断を行う場合は、できるだけ腫瘍全体を切除して病理検査を行い、その診断をもとに治療方針を決定します。
画像検査
ダーモスコピーや皮膚生検を行って皮膚がんだと診断され、さらに他の内臓などに転移している可能性がある場合は、エコーやCT、MRI、PET-CTなどの画像検査を組み合わせ、全身への転移があるかどうかを調べます。
皮膚がんの中でも進行した悪性黒色腫や有棘細胞がんなどには、この画像検査による全身検索を行うことが重要です。
進行度によっては、治療後も再発や転移がないか調べるために、定期的に画像検査を行うことがあります。
皮膚がんの治療方法

皮膚がんは転移がなければ手術で切除することがほとんどです。
ただし皮膚がんは種類や進行度によって治療方針が異なるため、薬物を使用した化学療法や放射線療法などを行うことがあります。
ここでは、皮膚がんの治療方法について詳しく紹介します。
手術
上述の通り、皮膚がん治療の第一選択は手術です。
肺や肝臓など他の内臓への転移がない場合や、手術で病変をすべて取り切ることが可能だと判断された場合に選択されます。
ただし、がんの種類や大きさによってはセンチネルリンパ節生検(最初に転移する可能性があるリンパ節を切除する)や、リンパ節郭清(周囲のリンパ節を広く切除する)、術後の化学療法を併用することがあります。
なお、悪性黒色腫や基底細胞がん、有棘細胞がんなどは顔などの紫外線の影響を受けやすい部位や手足などに生じるケースが多いため、術後の見た目や機能面を考慮して手術が行われることもあります。
薬物療法
皮膚がんに行われる薬物(抗がん剤)を用いた化学療法には、内服で行うものと点滴で行うものがあり、どちらも外来通院で治療を受けることが可能です。
従来の抗がん剤は、皮膚がんへの効果が期待できませんでしたが、免疫チェックポイント阻害薬(免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ薬)や分子標的薬(病気の原因となっているタンパク質などの特定の分子のみに作用する薬)などの新薬の登場により、効果的な治療が行えるようになっています。
放射線療法
皮膚がんの種類により、放射線がよく効くがんであると判断された場合や骨や脳、他の内臓などに転移している場合は、放射線療法が適応となる場合があります。
放射線療法では、がんの縮小や死滅を目指し、がんのある部分に可能な限り放射線を集中させます。
がんの種類や発生部位にもよりますが、1日1回、約10〜15分の治療を週5回ほど行い、それを数週間連続して行うのが一般的ですが。
治療効果を高めるために、薬物による化学療法を併用することもあります。ただし、その分副作用のリスクも高まってしまうため、慎重に選択することが大切です。
まとめ
ほくろと悪性黒色腫などの皮膚がんは、見た目が似ていることもあるため、見分けるのが難しい場合もあります。
今回、ほくろと悪性黒色腫の見分け方を紹介しましたが、あくまでも簡単にチェックするためのものです。
皮膚がんの種類によっては他の内臓やリンパに転移する可能性もあります。気になるほくろや皮膚の色調の変化などがある場合は、早めに医療機関へ相談しましょう。
成増駅前かわい皮膚科では、正確な診断のためにダーモスコピー検査や生検による病理検査を行い、腫瘍の種類に応じて適切な提携病院を紹介するなどしてより専門的な治療を受けていただけます。
ほくろがだんだんと大きくなってきた、ほくろから出血したなど、不安な症状がある方はぜひ一度成増駅前かわい皮膚科までご相談ください。
記事制作監修

成増駅前かわい皮膚科
院長 河合 徹